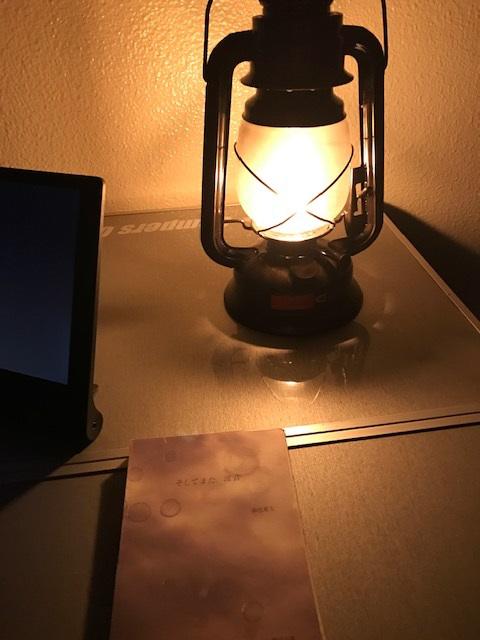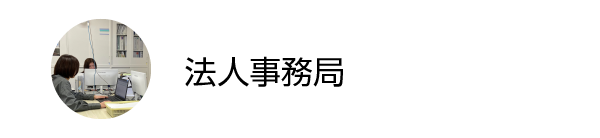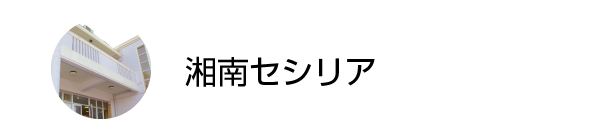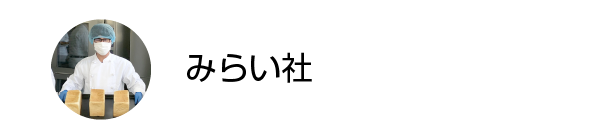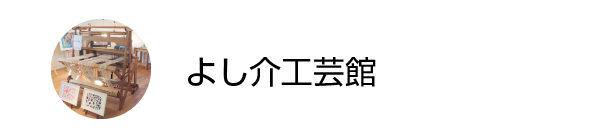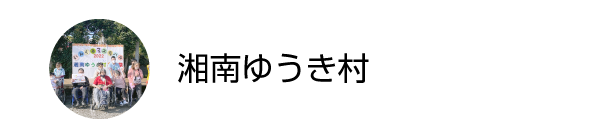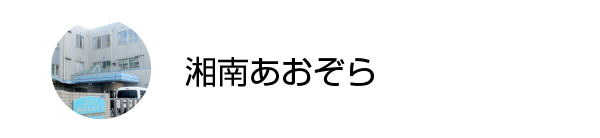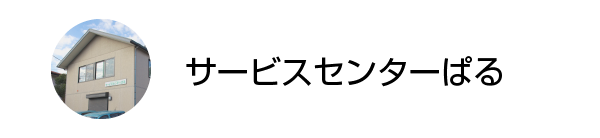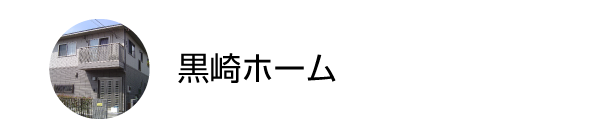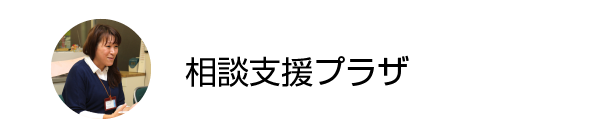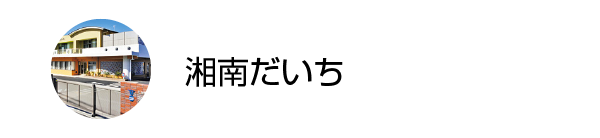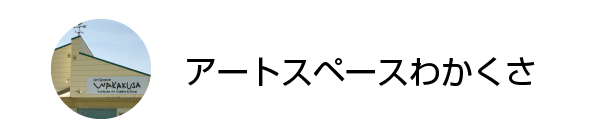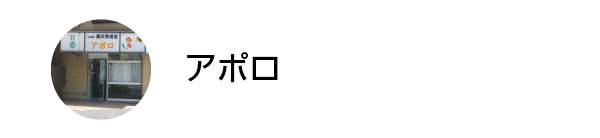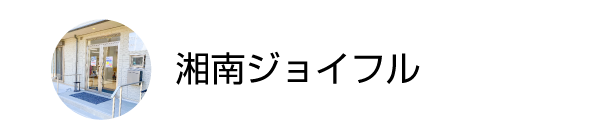日記
サービスセンターぱるの施設長・課長日記
『父権主義からの脱却を・・・』( サービスセンターぱる・湘南ジョイフル / 副所長 宗像 喜孝 )

ここ数年大好きな秋が短くなっているようで、残念に感じることが多い。数十年後には、四季を感じることができる日本人が少なくなっているかもしれない。息子や娘が一緒に外出をしてくれる今のうちに、子どもたちに日本の四季の良さを伝えていきたいと思う。
さて、9月20日発刊の福祉新聞にて、『国連の障害者権利委員会が日本に対する初の勧告として、障害児・者の施設収容廃止(脱施設化)を求め、地域で他の人と対等に生活するための支援に予算配分を求めた』という記事があった。見出しには「父権主義からの脱却を・・・」とある。勧告の中では『「グループホームを含む特定の生活様式に住むことを義務付けられないように」と念を押した』とも書いてあった。父権主義とは、パターナリズムの日本語訳として用いられ、意味としては、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することをいう。福祉に携わっている人でさえ、「父権主義」の活字だけ見て、パターナリズムの意味と解釈するのは難しいのではないか。あらためて、異国の概念を日本語訳することの難しさを感じる。
記事の中では、国連の障害者権利委員会は、グループホームを脱施設化の対象施設として認識しているのが分かる。直近の津久井やまゆり園の再整備の動きや今の日本の福祉サービスの制度設計をみると、日本は上記の世界基準とは程遠いと感じることが多い。今年度、法人の3つの重点項目の中の1つの取り組みとして「日常を"社会的スケール"で見つめ直す」をテーマに取り組んでいる。個人的には、"社会的スケール"とはもちろん日本国内の概念だけではなく、世界的なスケールとも密接に関連していると捉えている。こういった機会を捉えて、世界の福祉の動向を注視することも大切であると感じる。
以前の日記にも書いたことがあったが、藤沢育成会への就職が決まり、入所施設に配属されたことを当時の大学のゼミの恩師に伝えた際、「今後、日本の入所施設は解体されるから、貴重な経験だと思って頑張りなさい」と背中を押してくれたことを思い出す。
(写真)3年ぶりの家族旅行で、栃木県の東武ワールドスクウェアへ。学生の頃のように、いつの日かまた本物のサグラダファミリアを見にスペインへ行きたい・・・。
波多江式インディアン的福祉論⑳ ~番外編:かけがえのない人~ ( サービスセンターぱる / 所長 波多江 努 )
私には心の師と仰ぐ利用者が3名おり、その1人から「生きること」を学ばせてもらった経験があります。
ひと昔前のことではありますが、師はある理由で脳が委縮し、自分でできることが徐々に減り、大半の場面で介助が必要となったのです。食事を摂取することも困難な状態となり、師の家族は当時の主治医から胃ろう造設を勧められたのです。造設しなければ、徐々に衰弱していくことは言うまでもありません。しかし、家族はそれを拒否したのです。
当時の私は、その判断に大きく動揺しましたが、受け止めざるを得ませんでした。変化していく本人の状態に合わせ、今できることを考え、家族と相談し、支援してきました。
数か月後、本人の生涯を振り返った家族の手記を頂戴する機会がありました。何度も通読することで、家族は師が生まれてから様々な現実を受け入れながら、師を心から愛しており、また師も家族を愛していたことが伝わってきました。(この手記は、今でも私にとって大切なバイブルとなっています。)
あの時の胃ろう造設の拒否は、家族が師に対し、最大の敬意を払いながら「これまで家族のために生きてくれてありがとう。あとはのんびり暮らそうね。」という想いを踏まえた上での判断だったのだと思います。
十数年たった今、私に同じようなことが起きています。
近親者が常時介護を必要とする状態となり、医師からは胃ろう造設を勧められ、拒否することは殺人行為と同じ。と行き過ぎとも思える話を受けました。
しかし、私たちが出した結論は、師の家族と同じです。
「あなたからの優しい気持ちは存分に感じてきました。ありがとう。あとは、のんびり暮らしていきましょう。」
そして、師とご家族の皆さん、かけがえのない経験をさせていただき、生きることを学ばせていただきました。本当にありがとうございました。
今年の夏は!( サービスセンターぱる・湘南ジョイフル / 課長 大澤 健二 )

こんにちは。サービスセンターぱるの大澤です。
前年度まで、みらい社でしたが、今年4月より、サービスセンターぱると、湘南ジョイフルの支援課長として働いています。
さて、梅雨も早々に明け暑い日々が続いていますが、体調変わりないですか。
私は、暑いのが苦手ですが、なぜか今年は、今のところ耐えられています。
それは何故だろう・・。前々回の日記に、『健康第一は本当に大事だった』と、健康について触れた内容を書いたのですが、きっと、その効果の一つなのも知れないと思っています。
昨年の夏、仕事も休日も色々できなかった事がありました。今年の夏は、色々やれた!と、感じられる夏にしたいと思います。
皆さんは、どんな夏を描きますか?まずは、資本となるお身体ご自愛下さい。
『秘密基地はもう作れない・・・!?』 ( サービスセンターぱる・湘南ジョイフル / 副所長 宗像 喜孝 )
6月のジメジメとした梅雨時期の天候がどうしても好きになれない。気圧の関係か偏頭痛が続く日が多い、湿気で肌がべとついて一日不快感がある、悪天候の日が多いので外出が億劫になる・・・。天気に争っても仕方のないことだが、自分はやはりすっきりとした秋晴れを感じる季節が心地よいと感じる。コロナ禍における、いわゆる「おうち時間」の過ごし方について、この数年工夫を重ねてきたので、悪天候の日にはそういった経験をぜひ生かしていきたい。
さて、小学生の頃、近くに住む友人を集めて、よく周辺の空き地に「秘密基地」という名の集いの場を作るのが楽しかった。家の近くの裏山、工事現場、マンホールの下の空いたスペース等、その時々に流行る遊びに合わせて、コンセプトの違う秘密基地を作っていった。実家はマンションだったこともあり、ペットを家で飼うことが出来ず、野良猫やカメ、ザリガニ、モグラ(?)などを秘密基地に持ち込んでは、友人と持ち回りでエサを調達しながら、そこでこっそりペットとして飼うこともあった。また、秘密基地内のレイアウトにもこだわりがあり、粗大ごみ置き場に捨ててあったテレビや小さい冷蔵庫、ソファーやデスク、照明などを友人とせかせかと運び出し、もちろん電気は通っていないので使えることはできないが、運び出したものを並べながら、秘密基地の雰囲気を楽しんでいた。
自分の息子や娘の話を聞く限りでは、今の子どもたちはそんなことをしている子はいないらしい。そもそも秘密基地を作れるような空き地が見当たらないという。先日、息子から友人とバトミントンをしたいがやれる場所がない旨の話を聞いた。近くの駐車場やその辺の空き地でやれば良いではないかと言ったが、駐車場は車を止める場所なのでやってはいけない、そして「空き地」とはそもそもどこの場所を言うのか、という返答だった。子どもにとっての安全性や不法侵入や器物破損などの法的な問題など、起こり得る事故やケガ等のトラブルを想定して、大人も子どもも場所の意味を明確にしておくことは必要だが、遊び場のない現代の子どもにとっては窮屈に見え、杓子定規の効率的な考え方ではなく、もう少しゆるやかな認識があっても良いのではないかと思ってしまう。意味と意味の間には、グレーな部分が必ずあり、時にお互いの齟齬や摩擦を生んでしまうことがある。
今年度法人の目標にも掲げている『日常を"社会的スケール"で見つめ直す』にもつながる、「折り合い」のつけ方について考えさせられることがあった。
(写真)2020年9月愛甲郡清川村にて。早く気兼ねなくキャンプを楽しみたい・・・。
【波多江式インディアン的福祉論!? ⑲】 ( サービスセンターぱる・湘南ジョイフル / 所長 波多江 努 )
作者不詳のインディアンの言葉に
「分かち合うことが出来れば、悲しみは半分に、喜びは2倍になります。」
というものがあります。
この言葉は、人に寄り添うことの本質が表現されていると思います。
皆さんにも悲しみや悩みや苦しみを半分にしてもらえる人がいますよね。
嬉しいことや楽しいことを倍にしてもらえる人がいますよね。
それは、家族や友人、仕事の仲間かもしれません。
また、利用者と支援者という関係かもしれません。
できごとによって、分かち合いたい人が異なる場合もあります。
知っておいてほしいのは、
あなたの悲しみを半分にするために
あなたの喜びを倍にするために
私たちが存在しているのです。
ちょっと、カッコつけてしまったので、
「(私の将来の夢)インディアンになる」ための修行も倍になったかもしれません...(笑)
「小人の靴屋」 (サービスセンターぱる / 所長・事務局長 石川 歩 )

オミクロン株の流行が収まりません。法人内でも多くの事業所がクラスターとなり、利用者、ご家族のみなさま、関係者の方々にご心配をおかけしております。可能な限り感染拡大を防ぎ、一日でも早く終息を迎えられるよう、事業所間でも連携を図りながら努力してまいりたく存じます。
さて、話は変わりますが、今年度藤沢育成会事務局では、パソコン操作に明るい職員が中心となり、試行的にRPAの導入を行っています。
RPAとは、ロボティック・プロセス・オートメーション(Robotic Process Automation)の略になります。人の手で行っていた業務や工程について、ロボットに業務をやってもらうことをいいます。まるでグリム兄弟の童話にある「小人の靴屋」が実現したかのような技術です。
現在、会計業務の一部をこのRPAを活用して自動化しています。まだまだ試行段階ではありますが、実際に自動で動いているパソコン画面を見ていると、感心すると同時にいつかコンピューターに仕事を取られてしまうのではという焦りを覚えます。
実際に使ってみた感覚では、RPAはデータを別のシートに書き写したり、単純な作業を繰り返したりするのが得意なようです。反対にパターンや条件付けが複雑で変化するものはまだまだ人間の手が必要に感じます。
上手く最新技術を生かしつつ、職員の働き方改革に繋げていき、結果として支援の充実に繋げていきたいと考えています。
写真は文章とは全く関連がありませんが、2022年2月22日は鎌倉時代以来800年ぶりに2が6つも付く日、とのことで今までも時々登場している我が家のネコの写真になります。