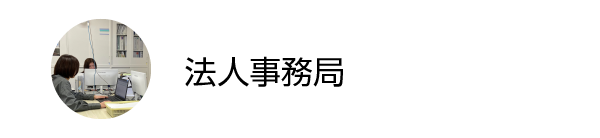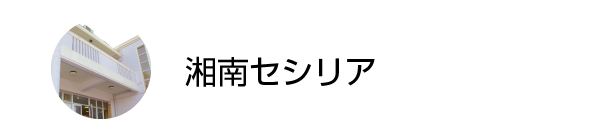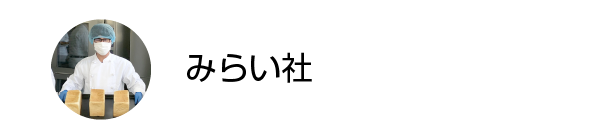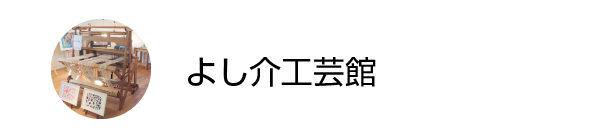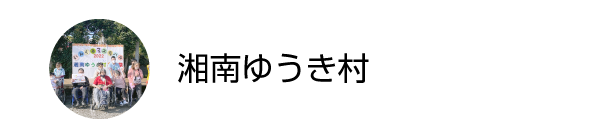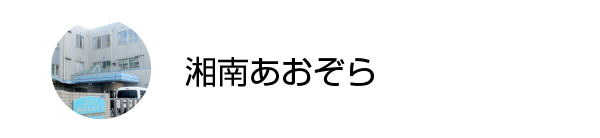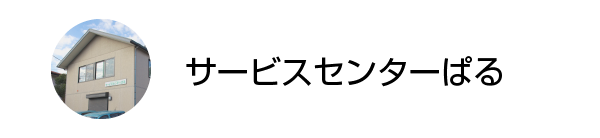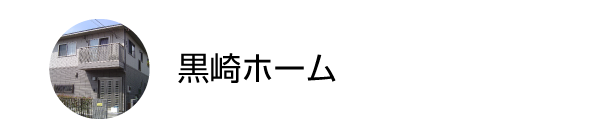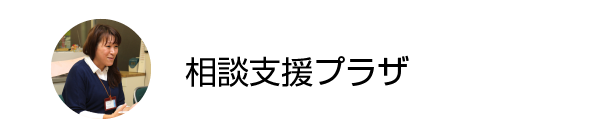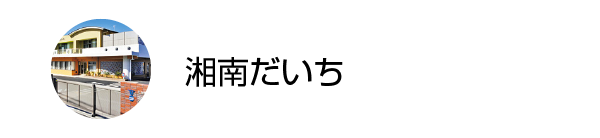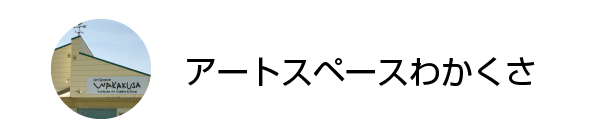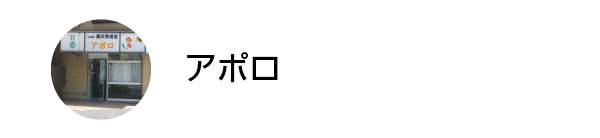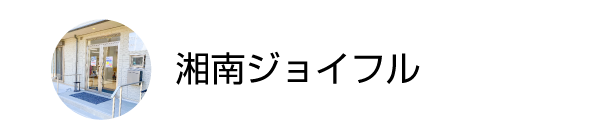日記
- HOME
- 施設長・課長日記
施設長・課長日記
「新年」(よし介工芸館・アートスペースわかくさ課長 石田 友基)
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
よし介工芸館・アートスペースわかくさでは、年明けに利用者さんと書初めをすることが恒例となっており、今年も皆さん想いを書いていました。
ふと、「書初め」について気になり、調べてみました。
書初めの意味としては
・字が上手になるように願う
・一年の目標や決意を決める
・心を新たにする
・やる気を持って行動を始められる
などの意味があるそうです。(AIによる概要 引用)
何気なく抱負や願いを書いていましたが、こうやって意味を知ってから取り組むとまた違った心持ちで字を綴れるようなきがします。
個人的には今年は前厄であり、去年から徐々に健康に不調をきたすことが増えてきたので、「健康第一」な年にしていきたいと思います。
半径5m(相談支援プラザ・よし介工芸館・アートスペースわかくさ 施設長 小野田智司)
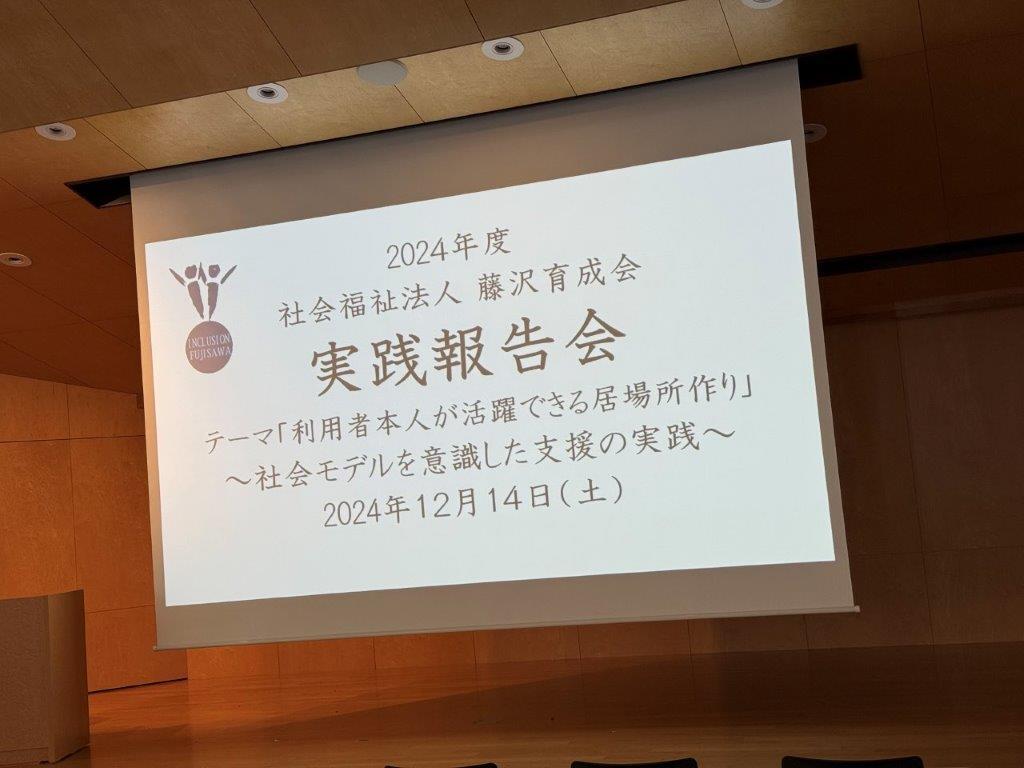
2025年になりました。
本年もよろしくどうぞお願いいたします。
2024年度母校で開催された
公開講座に複数回参加しました。
卒業生だけでなく、一般の方も含めての講座です。
教授より、問題提起がなされたのちに
参加者がそれぞれ今の自分のことを話し、
参加者の皆で応じるように意見交換し
深く考える場となりました。
私は「半径5m」の話をしました。
いろいろな支援計画書や
いろいろな会議は大事だけれども
やはり大事なのは、その「人」の日常の様子です。
「半径5m」
触れられそうで触れられない距離。
少し広そうですが、その方の様子はよくわかる距離。
ちょっとした雑談、
ちょっとした行動、
その範囲のなかの職員さんや環境、
その「ちょっとした」ことが
半径5mをみることで見えてきます。
ほかの参加者からは
能登半島地震および豪雨災害への対応について
ただボランティアとして泥をかき出したり
物を運んだりするのではなく、
住まう人の想いに寄り添いつつ
何気ないお話をすることのほうが求められている
けれど、ずっとはいられない...
など苦悩していることを共有がありました。
ほかにも
津久井やまゆり事件の話、
成長に心配する子育ての話、
とある施設での話、
様々な話の共有がありましたが
多くの共有点は
やはりその人の想いを基本に考えるということでした。
「半径5m」
皆様もちょっと意識してみてください。
■表紙の写真■
実践報告会
テーマ「利用者本人が活躍できる居場所作り」
~社会モデルを意識した支援の実践~
今年も盛りだくさんの内容で
写真や映像資料を示しながらの報告もあり
書面では気づけないことを
たくさん学ぶことができました。
日常から地域の方々との
継続的なつながりが
いかに大事か。
基本的な挨拶を継続します(^^♪
お城エキスポ(湘南あおぞら・アポロ 課長 髙橋羽苗)

チケットをいただきお城エキスポというイベントに行ってきました。
名前の通り、お城にまつわる展示や講演、ステージなどが一同に開催されるイベントです。
歴史的なものに興味はあるけれども詳しくはない私は、普段の観光でも「近くにお城があれば行ってみようかな」というほどで、わからないことがほとんど。イベントでも専門的(?)な言葉はわからないこともあり、いくつかの説明はいかにもわかったようなふりをして聞いてきました。
イベントの参加者は年齢層も幅広く、出展者と専門的な知識(?)で語り合っている方や、 家族で参加している方、歴史上の人物の衣装を楽しんでいる方など、会場はみんな思い思いに楽しめる雰囲気。
こういったイベントに行ってみると自分の趣味と言えるものが答えられない私としては、趣味や好きなことを楽しめる人たちを羨ましく感じます。あのパワーはやっぱりすごい。
そんなパワーに最初は圧倒されましたが、共通の興味を持ちながらも各々の楽しみ方で過ごしている空間はとても印象的でした。
イベントの一つに観光情報のエリアがあり、お城や武将、街の魅力などがPRされていて、私も気になるお城を発見。私も次の楽しみのきっかけをみつけたので、いつか行ってみようと思います。
▲かなり前に行った彦根城
『勝ち切る覚悟~ALL ROR THE WIN!』( 湘南あおぞら・アポロ / 施設長 宗像 喜孝 )

横浜DeNAベイスターズのファンの皆さん、日本シリーズ優勝おめでとうございます!!リーグ優勝は果たせませんでしたが、リーグ3位からの26年ぶりの日本シリーズ優勝はまさに圧巻でした。クライマックスシリーズから日本シリーズの最終戦までの間で、これほど個々の選手が成長し、チーム力が向上したチームを今まで見たことがありません。
父の影響で小学校の低学年から野球をはじめ、その頃から前身の大洋ホエールズ「友の会(ファンクラブ)」に加入するなど、足掛け40年ちかくベイスターズ一筋でチームを応援してきました。決して、毎年良い成績を残すわけでもなく、優勝争いに絡むことも多くないチームなので、今回の優勝は、感慨もひとしおです。
26年前は、横浜駅周辺で友人とテレビ中継を通じて試合を観戦し、優勝が決まった後は、そごう横浜店のからくり時計の前に大勢集まったファンと大騒ぎし、当時の監督であった権藤監督のマネをして代わる代わる胴上げをし合うなど、朝まで盛り上がりました。
今回は、好きな選手の名前の入ったタオルを身に纏いながら、家族と家で観戦し、優勝後は、シリーズ中に選手が活躍した場面の動画をSNS等で探し、美味しいお酒と共に優勝の余韻をたっぷりと味わいました。
さて、次回の優勝は果たして何年後になるでしょうか・・・。来年以降ももちろんベイスターズファンとしてチームを応援し続けたいと思いますが、出来れば今回のように26年かかる前に優勝してもらいたいと願っています。頑張れ、横浜DeNAベイスターズ!!
(写真)今年、観戦した時の写真。まさかその時には今年日本一になるとは思ってもみませんでした・・・。
「多様性」(黒崎ホーム 課長 髙橋克之)

「うちのクラスのA君は自分の誕生日を知らないんだって」
ある日の食事中、娘が言い出しました。何か複雑な事情でもあるのかと警戒しつつも理由を聞いてみると、A君は外国の子でその国(宗教?)では誕生日を祝う習慣がないとの事。まさに場所が変われば普通も変わる、な話だなと感じました。ちなみに、子供の学校では各クラスでその月の誕生者を祝うプチ企画があるのですが、A君は去年は5月、今年は11月生まれと言って祝ってもらっていたそうです。「なんかずるいよね」と娘は言っていました。外国籍のA君は日本の風習の中でうまい事立ちまわっている様です。
子ども達が話してくれる学校での話は、実に様々な人物が登場します。 "納豆は必ず100回混ぜるマン""一人称が俺な女の子"などなど。子供たちが日々暮らしている世界は色々な個性で溢れています。その中で世間体というフィルターをつける事なく自然と相手の個性と捉え付き合っている様子でした。
これは、子供の世界だけの話しではないとも言えます。私の友人も(自分を棚に上げさせてもらうと)かなり個性的な人もいますが、だからと言って接し方が変わるわけでもありません。「多様性」というのは私たちの生活に普通にあるものの様な気がします。
昔から自然と存在している多様性。その事を殊更に強調し注目を集める事。これは逆に多様性という名のレッテルを貼り、どんどん個別化する事になりギスギスとした世の中になるんじゃないか。そんな事を考えながら子供の話しを聞いていた冬の夜でした。
写真はこの間飾り付けたクリスマスツリーです。家は神道ですが、クリスマスも初詣もお盆祭りも楽しみます。多様性!
波多江式インディアン的福祉論㉗ ~~(黒崎ホーム 施設長 波多江努)
先日、ある方の仕事に対する姿勢に想いを馳せていた時に、ふと、インディアンの格言風に表現したら、どうなるだろうと思い、考えてみた。
- 頭で考えるのではなく、心で感じる人になりなさい。そして相手を知ろうとしなさい。
- あなたは誰かを救える特別な人ではありません。しかし、隣にいてくれる。
- イヤと言わない人間は、労う心を持っている。
この3つは、自分の中でも納得いくイメージであり、私自身が目指したい支援者像でもあります。
その方は、共感する力に優れ、時には利用者自身の問題を自分の問題と捉えすぎて本人の気持ちを置き去りにしそうな時もあります。しかし、ただ純粋に利用者の気持ちを理解したいと思っている少し不器用な方なのです。
私が困難に直面している時は見守ってくれていて、乗り越えた後に「大変そうでしたね」と声をかけてくれる方です。
利用者に対しても仲間に対しても尊厳を守る方です。
自分もそんな風になるにはもっと修業が必要だ...。