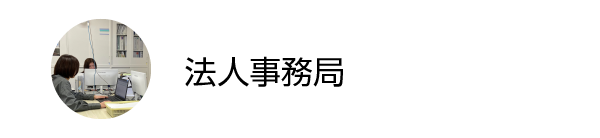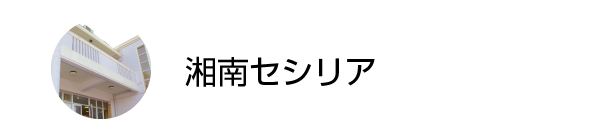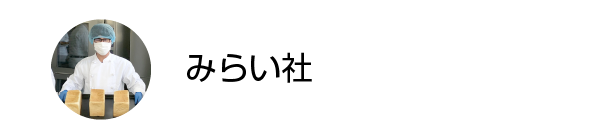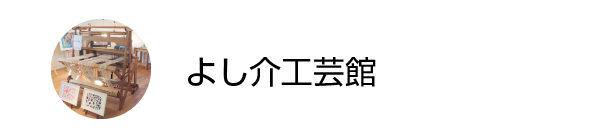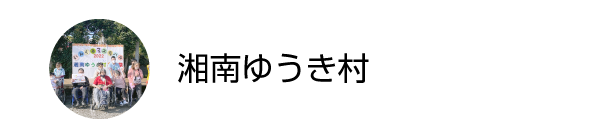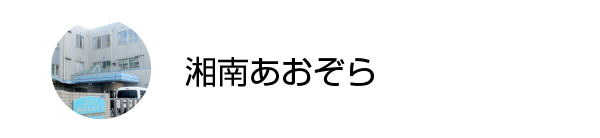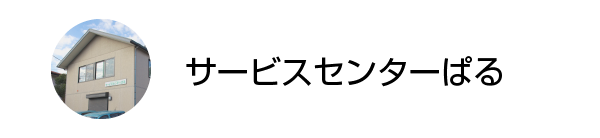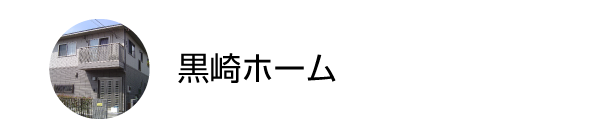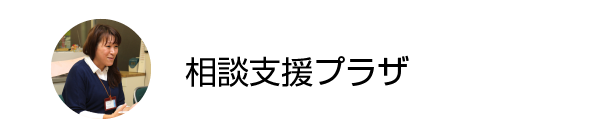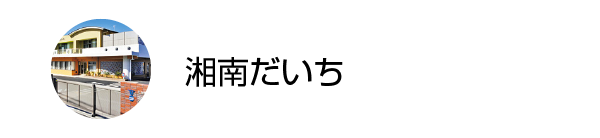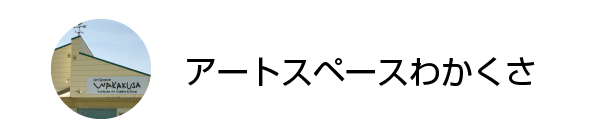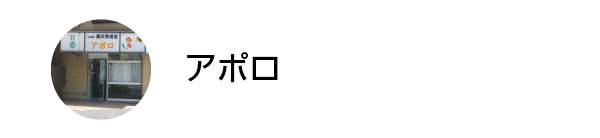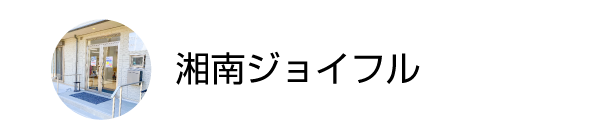日記
- HOME
- 施設長・課長日記
施設長・課長日記
「違い」・「間違い」(よし介工芸館・アートスペースわかくさ 課長 石田友基)
先日事業所内にて、コミュニケーションに関してグループワークを行いました。業務をする中で、意見が平行線を辿ったり、対立してしまうことは往々にして発生することだと思います。そこで、【意見が平行線(対立)となった時の、折り合いのつけ方や普段から気を付ける職員間のコミュニケーションについて考えよう】というお題でグループワークを行いました。
他者と意見が合わないとき、多くの場合は、「違い」であって「間違い」ではないということを聞いたことがあります。そのように考えると、話す側が伝わるように話す工夫は必要だが、それ以上に、聞く側の聞き方にポイントがあると感じました。そのためには、相手の言葉の表面にあるものだけでなく、言葉の背景に目を向けて、その考えや感情がどういった経緯から生まれたものなのか、それらに耳を傾け、分析し、整理をしていく。そうすることで、自分との「違い」が明確になり、次の話の展開につながり、建設的な話し合い、折り合いにつながって来るのだと思います。これが、感情に捉われてしまうと本質(目的)が見えなくなり、「間違い」に発展し、うまく意見交換することができなくなる要因だと感じます。簡単な話ではないが、やはりコミュニケーションは日頃から話しを聞く姿勢や態度、心のゆとりを整え、聞く姿勢を持つことが大切であることを改めて感じることができたワークでした。
写真は24時間エアコン完備で誰よりも涼しい部屋にいるくせに、暑さのせいか溶けている家のウサギです。
50年(相談支援プラザ・よし介工芸館・アートスペースわかくさ 施設長 小野田智司)

先日、両親の金婚式のお祝いを
家族が集まり行いました。
50年......
80代の父と70代の母
結婚当初は
30代の父と20代の母
50年.
月で云えば「600か月」
日で云えば「18,262日」
そんな長い年月の中で
きっと"喜怒哀楽"様々なことがあったのだと思います。
子どもを育てるながら
単身赴任があったり
大きな病気や怪我をしたり
祖父母の介護に向き合い
今では孫の世話もしてくれています。
父と母、それぞれにとっての
"主人公"となるエピソードがいくつもありました。
そのエピソードを皆できいて
大笑いしたり、ちょっとセンチメンタルになったり...
とてもあたたかいすてきなお祝いの場となりました。
―――――――――――――――――――――――
そして......
藤沢育成会も50年に向かって歩んでいます。
法人の前身である
地域作業所「星の村共同作業所」を開設されたのは、1978年。
今年で47年が経ちました。
もう少しですね。
今では「当たり前」と思える日常も、
制度の変遷の中で本当に様変わりしました。
特に印象的なのは、
障害のある方が
"福祉の対象"から"権利の主体"へと
変化したことです。
昭和の終わり頃でも「保護されるべき存在」として見られており、
福祉は"受けるもの"という印象が強かったと思います。
令和の今、障害のある方は"一人の市民"として
「権利を主張する主体」として位置づけられ、
差別の禁止、合理的配慮の義務化、意思決定支援の推進など
法整備も進んでいます。
次の50年。
60か月、18,262日のその先に......
私たちの今の「当たり前」と思える日常も
どのように変化していくのでしょうか。
とても楽しみです。
■表紙の写真■
金婚式を行った父母の家
孫にあたる世代に飾り付けを
頑張ってもらいました。
「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり。」(湘南だいち 課長 大澤健二)

梅雨時期となり、ジメジメとした日々が始まりますね。
私はこのジメジメが苦手で、この時期から低調となるのが毎年の事。それでも今年は何かと精力的に業務をこなしていくのだろう。と、考えながらホームページに載せる日記の題材を思い浮かべ・・・。
古人の名言を時々読むことがありますが、私の推しは武田信玄の名言です。
山本五十六の名言も強く惹かれましたが、やはり武田信玄の言葉はとても魅力を感じます。
藤沢育成会だけでなく、福祉業界は人財不足(ここではあえて財産の財を使わせていただきました)。
特に学生の就職先として『福祉』は選ばれる事は少なく、また就職した後の定着について福祉業界は若手不足が否めない状況に感じています。
ではなぜ、そうした状況なのかと考えますと、新型コロナウイルス感染症の対策が明確になり、様々な規制が緩和され始めた時期から企業の求人規模も広がり、学生が企業への就職を志望しやすい状況に戻った事も一つの要因なのかもしれません。
他では『魅力』も大きな要因と考えられ、企業には大きな『看板(人、社会貢献、待遇、賃金等)』と『人財確保と人財育成のスキルと戦略』をもって学生や若者たちへ『魅力』を発信しているのだと感じています。
福祉業界ではどうか。企業が持つ人財確保の戦略では到底及ばないものの『人を大切にする意識』では、企業と肩を並べるほどのものだと感じます。
経験年数や一人一人がもつ能力や期待する成長に応じ人財育成をプログラムし、成長を支援する事は最優先として取り組んでいると思います。
しかし、人財育成を目的として様々な研修プログラムを用意し実施していますが、入職から5年も経たず退職する事も少なくありません。
入職した学生や若手教育を丁寧に計画的に取り組む一方、そうした状況も人材不足につながっている事だと感じます。
自事業所や私が所属した事業所の職員が退職意向を相談してきた際、以下の事を若手の職員は教えてくれています。
・自分の夢や生活のために転職する。
・もっとスキルを身に着けるため、他の仕事(福祉)で働いてみたい。
・事業所の仲間はとても良い人だけど、組織(法人)に愛着が持てない。
・役職者が自分を大事にしてくれていると感じられない。
など、退職意向を伝えていただく際に話してくれた事です。
私自身、法人内の役職者として勤めるなか、自分の夢を描き退職を選んだ若手職員とは違い、組織や人間関係から退職を選んだ若手職員が話してくれた事を、今いる職員、これから就職しようとする学生や若手の定着のため、これからも活かしていきたいと日々留意して取り組んできたいと考えています。福祉の人財枯渇防止と質の維持向上のために。
まさに、人は城、人は石垣・・・。ですね。
神社で手軽な森林浴(湘南だいち いとぐるま・はんもっく課長 岩瀬一郎)

休日は、よく神社に出かけます。ほとんどの神社は、鎮守の森に囲まれており、参道を歩くだけで清々しい気持ちになります。手軽な森林浴です。樹木が発する「フィトンチッド」と呼ばれる物質に触れると、リラックス効果や精神的な安定、免疫力向上などの効果が期待できると言われています。ちなみに森は個々の樹木が独立して生活しているのではなく、「フィトンチッド」を介して集団で会話し、助け合いながら、自らの環境を作り守りながら生きていると言われています。
神社には御神木があり、古くから日本の歴史を見守ってくれています。熱田神宮の大楠は樹齢1000年を超えており、鎌倉時代から戦国時代に織田信長公が必勝祈願をした姿も見てきたでしょうし、太平洋戦争当時の名古屋大空襲でも焼かれずに残ってきました。私のお気に入りは三嶋大社の金木犀です。樹齢1200年を超えてもまだなお、秋になるとほのかな香りを漂わせています。
明治神宮の森は、人工林ですが、植樹から100年後に自然な雑木林になるように1915年に設計されました。様々な種類や高さの樹木が互いに支えあって共生し、自然の力によって世代交代を繰り返し、永続する自然の森を目指してつくられたそうです。明治神宮を参拝するたびに清々しい気分になります。
森林浴はしてみたいけど、登山やハイキングはハードルが高いとお考えの皆様、神社参拝で手軽な森林浴をしてみてはいかがでしょうか。
※写真は熱田神宮です。
骨髄提供体験記③(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明)

骨髄提供体験記の続きです。
これまでの体験記①②は下記をご覧ください。
体験記① 【通知~確認検査】
社会福祉法人藤沢育成会 | 骨髄提供体験記①(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明) | 施設長・課長日記
体験記② 【最終同意~採取前健康診断】
社会福祉法人藤沢育成会 | 骨髄提供体験記②(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明) | 施設長・課長日記
採取前健康診断にて、
麻酔科医の「呼吸が3時間止まる」という説明について確認したところ、
厳密には『自力呼吸が止まる』という意味であるとのこと。
呼吸を管理するために『人工呼吸器』を使用する必要があり、
その際には気管にチューブを挿入する『挿管』を行う必要があるとのこと。
なお、挿管の際には、喉を傷める可能性があることについても説明を受けた。
3時間程度で無事、移植前健康診断を終えた。
7月中旬【骨髄提供決定】
移植前健康診断を受けた数日後、結果が届いた。
『骨髄採取可能な健康状態』とのこと。
これで、正式に骨髄提供が決まった。
候補者の間は『提供しない可能性』もあるので上司以外には伏せていたが、
決定したタイミングで湘南ゆうき村の職員にも伝え、
今後の通院や入院について報告した。
7月下旬【自己血採血】
自分の血液を採るために病院へ。
骨髄を採る=体内の血液量が減る
その為、事前(手術の1~2週間前)に
自己血を採って保存し、手術中に戻す必要がある。
私は1回400mlの採取だったが、
2回に分けて800mlほど採るケースもあるとのこと。
採血中、看護師さんから
「患者さんの体重等によって、骨髄採取する量が決まるんですよ」
と教えてもらい、
「ということは、子どもなのかな?それとも女性?」
なんて勝手に想像しながら、30分程度で自己血が採れた。
自分の血を自分に戻す準備・・とても不思議な感じ。
この時期、自身の体調管理にはこれまで以上に敏感になっていた。
というのも、患者さんはすでに前処置(抗がん剤治療など)に入っており、
もし私が体調を崩してしまえば、骨髄提供そのものが中止になる可能性がある。
「自分の健康が、誰かの命に直結する」
そう考えると、ちょっとした喉の違和感や倦怠感にも神経質になる毎日。
振り返ってみると
骨髄提供までのプロセスで、いちばん辛かったのは、
身体的な負担よりも、「ちゃんと提供できるだろうか」という
そのプレッシャーだったのかもしれない。
今回はここまでにさせていただきます。
次回は入院の様子をお伝えできればと思います。
写真は、『花よりだんご虫』の娘たち。
公園で散歩中、色とりどりの花が咲く中で、
「せっかくだから、花を背景に笑顔の写真を撮ろう!」
と、親として期待がふくらみます。
ところが娘たちはというと......
咲き誇る花には目もくれず、
しゃがみこんで夢中になっているのは地面。
視線の先には、1匹のだんご虫。
「見てー!丸くなったー!かわいいー!」
花なんて目に入っていません。
2人の関心は完全に『花よりだんご虫』。
何度呼びかけてもこちらを見てくれず、
花をバックにした笑顔の写真なんて、撮れるはずもありません。
でもふと、「いや、これでいいんだな」と思いました。
咲いている花の美しさよりも、足元の小さな命を見つけて心を躍らせる姿。
その自由さと感性こそが、今しかない子どもの瞬間なのかもしれません。
思い通りの写真は撮れなかったけれど、
花よりだんご虫に心奪われるその好奇心と自由さに、
なんだか嬉しくなってしまいました。
大人の「こうあってほしい」を
軽やかに裏切ってくれる子どもたちの姿に、
学ぶことは多いなと感じた春の一日でした。
深緑・深呼吸(湘南ゆうき村・湘南だいち 施設長 妹尾貢)

5月に入り、新緑だった木々の緑がどんどん濃くなっていく季節です。気温が上がるにしたがって、空気に含まれる香りが豊かになり、ふとした瞬間に古い記憶が呼び覚まされることがあります。それを確かめようと、もう一回大きく空気を吸うと、次の瞬間にはもう空気が変わってしまい、記憶も遠くなっていつのどこのことか、はっきりと認識できないけれど、でも確実にその時の気持ちがよみがえります。
世の中が便利になって、身体を使う必要が少なくなっているためか、それとも年齢のせいか、大きく息を吸うようなことが減っているように思います。
近所の市民プールの改装が終わり、一時休止していた水泳を半年ぶりに再開しました。といってもいつまで続くかわからないマイブームです。
中高生の全盛期の水面を滑るような感覚を身体が覚えているので、現在の沈み加減に歯がゆい思いをしますが、それでも、呼吸法を思い出せば、循環器系は結構戻るものだということを発見しました。
深呼吸というとラジオ体操のように「大きく息を吸って~、吐いて~」という順番に思いがちですが、呼吸が浅くなっている人が、いきなり息をたくさん吸おうと思ってもうまくいきません。まず、吐く必要があります。もうこれ以上吐き出せない、というところまで空気を吐き、さらに絞り出します。これが出来れば、吸うほうは自然にできます(苦しいですから)。
吐いて吸う、帰って行く、暮れて明ける、止んで降る、捨てて手に入れる、死んで生まれる...
繰り返し起きる事象の時系列を入れ替えてみると、ものごとの本質が見えてくるような気がして、これもマイブームです。
すべては、太陽と地球と月のバランスによる、回転運動でできあがっているからでしょうか。
写真は、通っている管理釣り場の風景です。水温や時間帯、昆虫の羽化の状況によって魚の活性も変わりますが、ふとした時に見上げる山の景色の移り変わりも楽しいです。