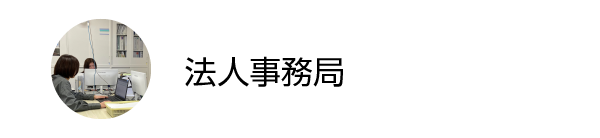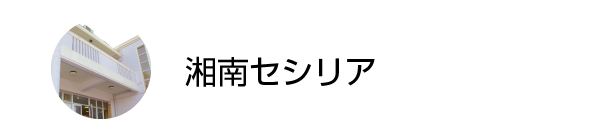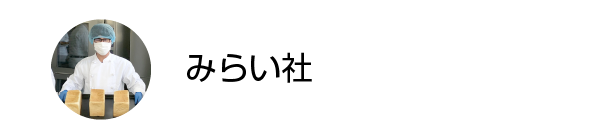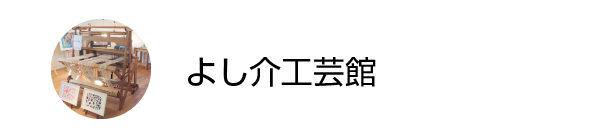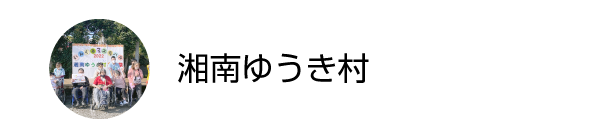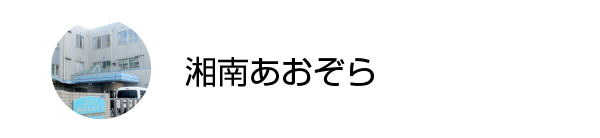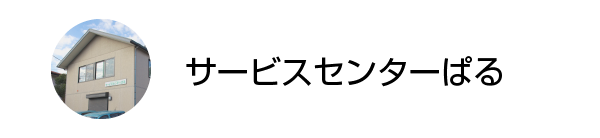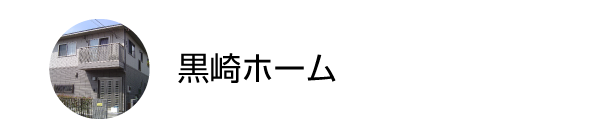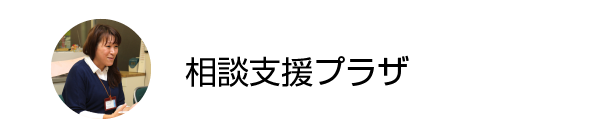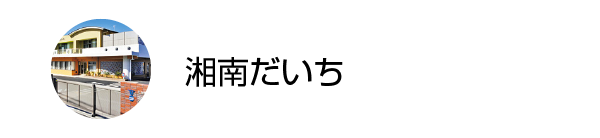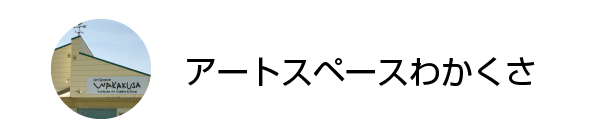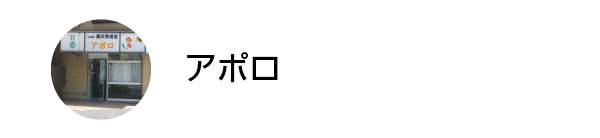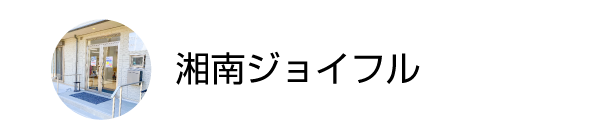日記
- HOME
- 施設長・課長日記
施設長・課長日記
専門職として、地域住民として (相談支援プラザ / 所長 小野田智司)

2022年、今年は藤沢育成会に入職し
20年目の節目の年です。
これまで
湘南あおぞら
サービスセンターぱる
湘南ゆうき村・相談支援プラザ
湘南セシリア
と勤務してきて、この4月より
相談支援プラザの所長として勤務しております。
これまでの19年、主に障害福祉分野において
様々な場面で経験や体験、勉強をしてきました。
その時その時
目の前にいる障害のある方が
どのような支援があるともっと楽に、
安心して生活が送れるかということを、
一定の経験や資格をもつ
専門職チームで一生懸命考えて
検討し工夫してきました。
ご家族とのやり取りでは
考え方や想いなどを推察しながら
支援について伝えるよう努めてきました。
それでもご家族の想いに
寄り添うことが出来なかったことも
あったと思います。
先日の話ですが、
ご近所の顔見知りの高齢のご夫婦と
おしゃべりをしていると
困りごとがあることがわかりました。
そのことを相談にのってくれる
とある機関のことを紹介したところ
安心されることなどがありました。
その後ご夫婦からは
こんなことを相談することなんて
思ってもいなかったし
実はどうしていいかわからなかったよ
などの話をいただきました。
相談支援プラザでは相談支援の専門職として
様々な方々へ相談支援を行っています。
その相談支援の場面で、
地域住民の当たり前の考え方も理解し
その上で専門職チームとして
相談支援をしっかりと行っていきたいと
ご近所のみなさんとの
触れ合いの中で気づいたところです。
■表紙の写真: 湘南とらい外観
一生モノの宝物 ( 相談支援プラザ / 課長 一戸香織)

何気ない日常は当たり前ではない...と感じる日々が続いています。
2022年春...
4月に入り、暖かな陽射しを浴びながら今年も変わらずに桜が咲いています。
この季節になると、
九州から引っ越して来られた方とお会いした時の話をふと思い出します。
その方は、
80年住み慣れた地を離れ、娘が近くに住むこの藤沢市に住む事を決めました。
「モノは持って行けないから最小限にね」と娘から言われ、言葉ではわかっていても、しばらくの間、ずっとモノが捨てられずにいました。
何度も何度も「持って来ても置く場所がないから、処分して来てね」と念を押されても、荷物整理は一向に中々進みませんでした。
とうとう、引っ越しの寸前に「こんなモノは捨てて」と終始娘に言われて、ようやくモノが減ったそうです。
元々住んでいた九州のお家の敷地には、桜の木が数本あり、廊下の戸を全て開けて近所の方とお花見をした思い出話を聞きました。敷地の広い、大きな家で生活していたのです。
引っ越し先のアパートの室内で、一つとても気になるモノがありました。
それは、玄関から部屋に通じる廊下のど真ん中に、ドンッと置いてある火鉢です。両手で抱える位の大きさのとても一人では持てそうにない位に重そうで、瑠璃色の鮮やかで綺麗な色でした。
ある日、私から「この火鉢は、玄関から出入りする時に、つまずいて転んだら大変なので、もう少し移動すると良いですね」と話しました。
その言葉から、いろいろ話して下さいました。
「娘からは、『絶対に(九州から)持って来たらダメ、必要ない』と言われたけど、
頼み込んで、持って来たモノなのよ」
「原爆の時に、全て焼けてしまった中から、一つだけ焼けずに残っていたのが、
この火鉢だったの」
「これだけは一生モノの宝物として、藤沢まで一緒に引っ越して連れて来たかったの」
私は、つまずいて転んだら骨折して、打ちところが悪いと大怪我に繋がると思い、火鉢を移動しましょうと話した...つまり火鉢は重たくて邪魔なモノと考えて、その方に伝えてしまったのです。ご本人の火鉢への思いを知っていたならば、もう少し違う言い方、伝え方をすれば良かったと思いました。
でもその方は即座に、「そうね、もう少し動かさないと転んだら困るからね」と言葉を返してくれました。
一生モノの宝物と言われた時に
みなさんはどんな宝物を思いますか?モノ、言葉、気持ち。
私にはあるだろうか、一生モノの宝物
~天神公園~
地域の方々が参加して公園体操をしています。
『2023年度の新卒採用活動が本格化します』 (法人事務局・湘南だいち・湘南ジョイフル / 課長 宗像喜孝)
2023年卒の学生を対象とした採用活動の広報解禁日である3月1日を過ぎ、藤沢育成会も他社に遅れることなく、採用活動を本格的にスタートさせました。実際には、採用につながる取り組みは、昨年の6月から開始したインターシップの申込みからすでに始まっており、足掛け半年以上になります。今から取り組みの成果がどのようになるのか楽しみでなりません。
今年度は昨年度用にコロナ禍の中、感染症予防対策の観点から、一般企業を中心に、他社はオンラインを活用した採用活動を行うところが目立ちました。藤沢育成会も昨年からオンラインのコンテンツを充実し、オンライン上で会社説明や障害特性に関する演習等を行ってきましたが、やはり学生のニーズは、福祉の仕事の特性もあり、実際の職場で、対面で実習をすることにあるのではないかと法人採用担当の担当者間で話し合いを行い、法人本部とリスクを協議しつつ、学生に2週間の健康観察と行動履歴の提出、その他厚労省のガイドラインを参考に実習の実施条件等を確認することを条件に、対面でのインターンシップを実施してきました。
結果として、多くの法人や企業が対面でのインターンシップを敬遠する中、当社比として昨年よりも倍以上の約70回以上の学生からのエントリーがあり、40日以上のインターンシップの実習を実施することが出来ました。採用活動の広報解禁日前に、学生といかに接点を持ち、法人に興味を持ってもらうかはとても大事なことです。このことが影響してか、すでに3月から始まった採用説明会では、インターンシップ実習を終えた学生が10名以上エントリーを行い、すでに説明会に来てくれた学生も数名います。
今や深刻な人材不足がどの業界でも叫ばれている時代であり、将来有望な学生が一人でも多く入社してもらうことが、法人の今後の発展に大きく影響を及ぼすことは間違いありません。例年、7月までに約全体の7割以上の学生が内定を受け、就職活動を終えると言われています。是非、これからの数か月、法人職員全員が法人の採用活動に注視してもらい、一体となって優秀な人材の確保に努めていければと考えていますので、ご協力よろしくお願いします。
(写真)中途採用者向けの説明会の一場面です。当社は、新卒者だけでなく、中途採用にも力を入れています!!
声を掛けること・掛けてもらえること(湘南セシリア / 課長 小野田智司)

少し前のことだが、テレビのバラエティ番組で
私としては驚くシーンがあった
それは寝転んでいる芸人さんの体の上を
別の芸人さんが自転車に乗り走行する
というものであった
バラエティ番組の中の複数の人たちは
一様に笑っていた
私は小学生の子どもと
一緒に視聴しており思わず
「これは無理だ。今日はもうチャンネル替えるね」と
声をかけ違うテレビ番組をみることにした。
翌日、子どもと昨晩のことを振り返ると
子どもなりに考えていたようで、
「あれは危ないよね」と言葉があり、
ほっとしたことを覚えている。
しかし笑いのためであったとして
怪我の恐れが高いことの
想像が容易い中で
その部分を放送したことに疑問を持った
集団心理からくるものなのか
忖度しているものなのか
だれか「危ない‼」と言えなかったのか
だれか「笑えない...」と言わなかったのか
現代はSNSを多くの人が活用しており
その時少し検索すると、
私と同じような感情を持っている人が少なからずいて、
そして、テレビ番組を支持する人も一定程度いた
でもそれは外野の声に過ぎない
バラエティ番組の中では
楽しく笑いが起きたシーンでしかない...
福祉施設で働いいていると
いろいろな価値観を持つ職員たちと仕事をする
大概「こうしたいなぁ」「こうだとこうなるかもね」など
前向きの話が多いが、時に意見が食い違い、
一定の答えをだすことに苦労する事もある。
でも気づいた意見を言えない
職員集団にはしたくないと考える
時に人は意図せずとも
良くないことをしていることがあると思う
そんなときはその気づきはきちんと
共有してきたい
共有してもらいたい
今年度はじめ、異動してきた職員に
私自身の言葉遣いについて意見をもらった
その瞬間は、負の感情が芽生えたが
すぐにうれしい気持ちにもなった
伝え方に工夫は必要だと思うが
声を掛けること
声を掛けてもらえること
それが当然のようにできる人で
ありたいと思う
2022年4月より相談支援プラザに異動になります。
相談の場にいる方が、ここに相談しようと決めて
行動に移すまでの想いをしっかりと受け止められるよう
これからも職員間、地域の方々と
声を掛け合っていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
■表紙の写真: 湘南セシリア外観
「元氣一番」 ( よし介工芸館・アートスペースわかくさ / 課長 儀保 治男 )
みなさんは、「げんき」という漢字を書くとき、「元気」と書きますか?
私は、「元氣」という書き方が好きです。以前の職場で、スクリーン印刷の作業を行っていたころ、「元氣一番」とTシャツの背中に印刷をしてほしいと依頼を受けたことがありました。依頼者に「元気の『き』はこの漢字でいいのですか?」と聞くと、「はい。それで良いんです。この『氣』は、中に米が書かれていて力が八方に広がる意味を表しているのです。一方、中に〆と書かれている『気』は、力が抑え込まれている感じがするのでこの『氣』でいいのです。」という話を聞き、それ以来、私の大事にしている言葉に「元氣一番」という言葉を追加しました。
みなさんの元氣の源は何でしょうか?普段の生活の中や自身の心の中に様々な「支え」があるかと思います。その「支え」が元氣の源となり、自分自身、また周囲を元氣にしてくれます。
心と体を整えてくれることば、『元氣一番』!!
「波多江式インディアン的福祉論!? ⑱」 ( サービスセンターぱる ・ 湘南ゆうき村 / 副施設長 波多江 努 )
作者不詳のインディアンの言葉に「信じることが価値を生む。価値は考えを生む。考えは心の反応を生む。心の反応は態度を生む。態度は行動を生む。」というものがあるそうです。
それぞれの言葉に関連性を感じ、矛盾の無さに優雅さを覚えます。
私たちが実践する支援は、「利用者を信じること」から始まります。
信じることは、「利用者への敬愛」という価値観につながります。
敬愛は「働くモチベーション」となります。
モチベーションは「支援者の日々の姿勢」となります。
姿勢は「具体的な支援やかかわり」となります。
簡単なことではないですが、この積み重ねが利用者の権利擁護やインクルージョンふじさわに発展していくのだと信じています。
雑誌の写真を参考にカチナ(インディアンのこけし⁉)を作ってみました