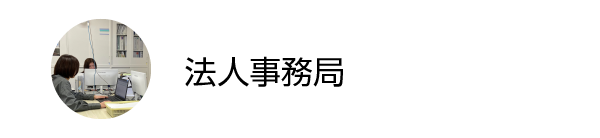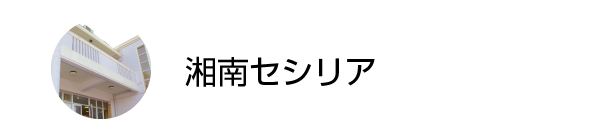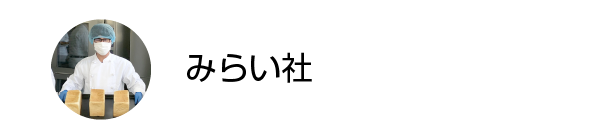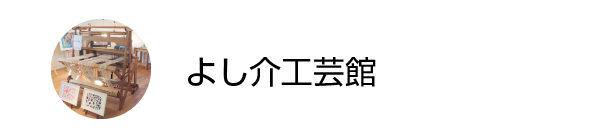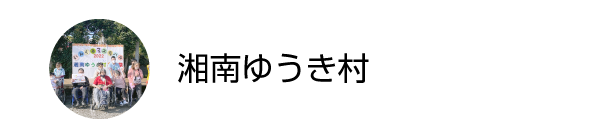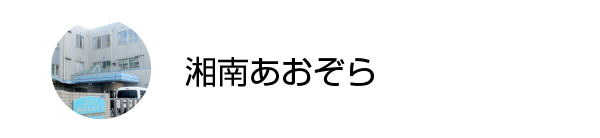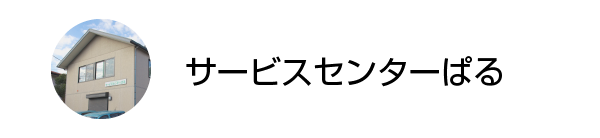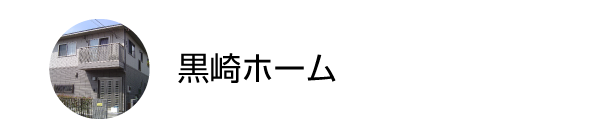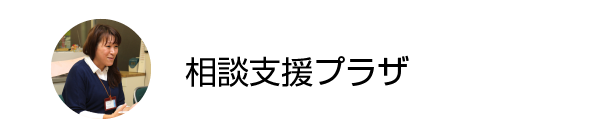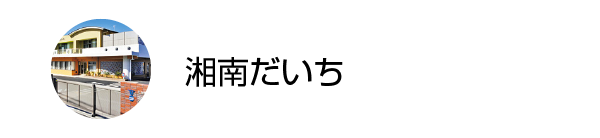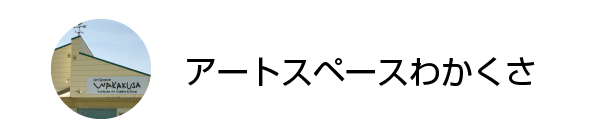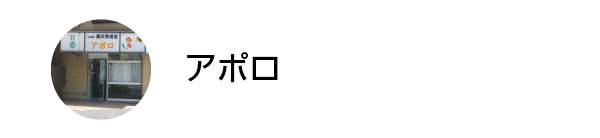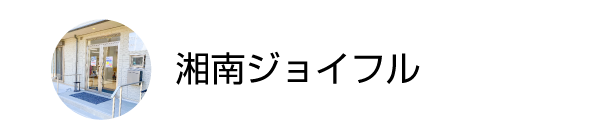日記
- HOME
- 施設長・課長日記
施設長・課長日記
『虹って何色ありますか?』 (湘南あおぞら 課長 石川 大助)
8月の雨上がりの朝、出勤のため自宅を出て住宅街を過ぎた辺りで空に虹がかかっているのに気づいた。それだけで嬉しくなりますが、よく見ると薄っすらともう一本かかっていて、なんと二重の虹でした。テンション上がって写真を家族にメール!
雨上がりではあるも、晴れているわけではないのにと思いまながらも、なんとも幸運を感じる朝でした。
その後、ちょっとスマホで二重の虹について検索してみると、虹にはいくつか種類がある事が分かりました。
主虹(一般的な虹)
副虹(二重に掛かる虹)
過剰虹(内側に繰り返すように色が見える虹)
反射光虹(水面等に反射した太陽の光が、再び雨粒に反射されてできた虹)
霧虹(太陽の光が霧に反射して見える虹)
月虹(夜に月の光で生じる虹)
水平虹(太陽の下の薄雲の一部に出来る虹)
夜に虹が見えることがあるなんて、なんとも幻想的な虹まであるのだと知りました。
日本人は『虹って何色(なんしょく)ありますか?』と聞けば「7色」と答えますが、ドイツでは5色、他にも8色、2色と答える国もあるようです。微妙な色を表現する言葉があるかないかによって違いがでるようです。さらには、見る側が虹を「何色と見ようとするか」によっても違うそうです。
言われてみれば、、、。小さい頃から虹は7色と耳にして、その色の分け方の概念が当たり前なので7色に見ようとしていますし、そうとしか思えません。画像を見ても7色のグラデーションの境を探すように色を数えてしまいます。
もし、自分が他の国で育ったら『3色です』『5色!』と当たり前に言っているかもしれないと思うと、育つ環境によってとらえ方がつくられているのだと改めて感じました。
余談ですが、虹を見て以来、通勤時に空を見上げる事が多くなりました。建物の上に広がる毎日違う空模様に魅かれてしまいます。
〜散歩道〜 (相談支援プラザ / 課長 一戸香織)

9月に入り、朝晩と過ごしやすい季節となりました。
コロナ禍の状況は変わらない中、働き盛りと言われている年代の方々がジョギングやウォーキングなどで身体を動かしている姿を見かける事が多くなりました。
昨年から始めたウォーキングも、冬の寒さや夏の暑さを理由に家に居る時間が増えていました。
気が付かないうちに、身体だけでなく心も何だかおとなしくなった気がしています。
「ウォーキング!」と構えて思うから、自分に密かなプレッシャーを掛けているのではないかとも思います。
ここ最近、何だかテレビの音や車の音、生活音が気になる様になっていたこともあり、季節の変わり目をきっかけに、今度は「散歩」として気軽に歩いてみようと思いました。
川の流れる音、鳥の声、耳を澄ますと日常生活の中で、忘れていた小さな音がとても心地よく感じました。
音を意識してみると、日常の中で気になる音がたくさんあると改めて気が付きました。
電話の声の大きさ、ドアの開閉、椅子に座る時など、様々な音は、自分だけでなく相手にも伝わる音でもあります。
仕事をする中で、日々慌ただしさや忙しさを感じる音・感じさせる音は、ちょっと配慮するだけで、様々なことをお互い話しやすい雰囲気に繫がる感じがします。
心地よく感じる音を意識しながら、日々の生活・仕事をして行きたいとあらためて思いました。
秋の夜長、様々な虫の声が聞こえて来ます。
ちょっと耳を澄ませる時間と心の余裕を持ちたいと感じた散歩時間でした。
「相模原障害者施設殺傷事件から5年・・・」 (湘南だいち・法人本部事務局 / 課長 宗像 喜孝)
コロナ禍で迎える夏休みも今年で2年目となりました。先日、息子が「ペットを飼いたい」と言い始めたのですが、我が家はマンション暮らしでペットは飼えないため、自宅のベランダでミニトマトを育てることにしました。この夏休み中、「ミニー」と名前を付け、ほぼ毎日自分で水やりや傷んだ葉を取るなどの世話を熱心にやっています。現在では、立派な実を沢山つけ、元が取れるほどの収穫が出来るようになりました。このコロナ禍で子どもたちが夏休みらしいことを経験出来ずに、何かと制限がありつまらない夏だと感じていると思いますが、いつの日か、「ミニー」との出来事を思い返し、微笑ましく家族で話せる日が来ることを祈っています。
さて、相模原市にある県立の障害者支援施設「津久井やまゆり園」で入所者ら45人が殺傷された事件が起きてから、7月26日で五年が経ちました。8月1日には、新しく再建された園で開所式が行われ、仮住まい先で生活されていた入所者約50人が新生活を開始しました。12月からは、仮居住先の芹が谷地域において、定員66人の「芹が谷やまゆり園」が開所されます。
事件が起こった日のことは今でも記憶に鮮明に残っています。当時、「津久井やまゆり園」と同じ、法人内の障害者支援施設で管理職として働いていました。起床してから、あることもないことも、これから起こるであろうことが目まぐるしく頭の中を駆け巡り、平常心を保つことだけを繰り返し繰り返し唱えながら、通勤したのを覚えています。植松死刑囚は、元施設職員ということもあり、職場でも類似した事件が起こらないか、今まで一緒に働いていた同僚、部下すら、事件を起こす可能性を考えざるを得ないと内心思うこともしばしばありました。
事件から5年・・・。この間、極端な議論も含めて多くのメディアで取り上げられ、国や各市町の自治体、民間団体等が事件を受けて、様々な取り組みがなされてきました。しかし、この事件で一番大切に取り上げられるべき、障がいのある当事者の生活において、目に分かるようなQOLの向上がなされたでしょうか。個人的には、事件において、当事者も含めてそれぞれが自分なりの考えを持つこと。そして、事件を風化させずに皆で議論を止めないことが大事だと思っています。是非、この5年を節目と捉えて、職場や仲間同士など、色々な場面で、この事件について議論してみてはいかがでしょうか。
10月から小田急江ノ島線の長後駅から徒歩3~5分の場所に、新規生活介護の事業所として「湘南ジョイフル」がオープンします。「障害があってもなくても当たり前の生活が、地域で送れる社会の実現」と「画一的ではない、当事者本人のニーズに合わせた多様な生活の在り方をサポートできる事業所」を目標としています。職員間でもこの事件について議論し、感じたことを日常のサービスに生かしていきたいと思います。
(写真)収穫時期の「ミニー」
散歩は時間、ジョギングは距離 (湘南セシリア / 課長 小野田 智司)

新型コロナウイルスワクチン接種について
藤沢市では7月30日時点で
1回目110,014回、
2回目72,654回まで
進んできました。
湘南セシリアでは接種を希望する方への
機会を設けるよう取り組んでいます。
藤沢育成会では、
強度行動障害者支援者養成研修「実践研修」の
事務局を担当しております。
2021年の3月、緊急事態宣言中の中、
2日間のプログラムをすべてオンラインに切り替えて行いました。
今年度も引き続きオンラインにて実施する方向で
県との調整を幾度もくりかえり行い計画しております。
さて、最近私の周りでは散歩を習慣化できている人が増えてきました。
私自身も去年の秋の検診で医師に
「コロナ太りだね」と
バッサリと断言され、
お散歩をちょこちょこと始めました。
3日坊主にならないように始めたのが、
Apple watchのワークアウト機能です。
歩いたコース・距離・時間・心拍数・消費カロリー・天気・気温が
連動するiPhoneに記録されいつでも振り返ることができるものです。
だいたい1時間くらいが基本ですが
そのうち気候が良かったりすると1時間30分くらい歩き
そして時折2時間歩いちゃうこともありました。
それも、終わった後にこれまでの記録を見直して
今日はこうだったなぁと簡単に思い出すことができるからかと思います。
そして、ついにゴールデンウイーク明けより
ジョギングの開始です。
最初はお散歩の途中でちょっと走る程度にしましたが
思いのほか走れることに気づきました。
そしてそこからはジョギングへ
最初は1時間くらいと思い走っていましたが徐々に、
今日は8キロメートルにしよう
今日はちょっと走る速度を上げるので4キロメートルにしよう
など、目安が「時間から距離」に変わっていきました。
もちろんiPhoneで確認する記録も時間数よりも
距離数に興味関心が向くように変化しました。
インターネットで調べてみると
多くの人が「散歩は時間、ジョギングは距離」で捉えているようです。
散歩からジョギングのちょっとした変化で
気になる単位が「時間から距離」へ変化する...
ちょっと驚きました。
障害のある方への支援をするなかで
自分と他者の"価値観の違い"にいかに気づくことを大事にしています。
今回また新しい価値観に気づき視野が広がりました。
「休日の散歩」 (よし介工芸館・アートスペースわかくさ / 課長 儀保 治男)
残暑見舞い申し上げます。
暑さ厳しい日が続いていますが、皆様いかがお過ごしですか。
暑さが厳しい時期は、私は朝活をして気分転換を行っています。
土日は、早朝3時半ごろに起床をし、あたりはまだ薄暗い中、ベランダに出て朝の涼しい空気を感じるのが休日の朝の定番となっております。
朝食を終えたら、近所の「散歩」のスタートです。コロナ禍の中、運動不足を解消すべく感染防止をしっかりとして散歩に出かけるのですが、この時期は、日が昇るとかなり気温が上昇し、汗拭きタオルが欠かせません。普段の散歩は、一万歩から一万五千歩歩きます。
最近、茅ヶ崎中央病院付近まで出かけたときに、工事現場の壁にいろいろな偉人や有名人の言葉が書かれていました。その言葉は、一つ一つが歩いている人に「勇気」を与えてくれそうな言葉ばかりでした。
その中で私が印象的だったのが、写真にある言葉です。日々の努力の積み上げこそが、いい結果に繋がっていくのだと改めて感じました。
まだ工事現場の壁は残っていると思います。もし近くを通りましたら工事現場の壁を気にしてみてはいかがでしょうか。
波多江式インディアン的福祉論!? ⑯ (サービスセンターぱる / 副所長 波多江 努)
アメリカ北東部の森林部族だったソーク族に「師は教えることでまた学んでいる。」という言葉があります。
師をどちらの立場でとらえるかで異なりますが、利用者を「職員を育てる師」とすると、伝えることで意思形成や意思決定のさらなる学びとなり、支援者を師とすると、支援を通じ、学んでいることは言うまでもありません。
私は、入職してから多くのことを利用者から教えてもらってきました。専門職としての学びはもちろんですが、多くの利用者とのかかわりを通じ、生きることそのものを教わってきた気がしています。今でも、私の仕事のモチベーションは学びを与えてくれた利用者への恩返しです。
この言葉の本質は、「自分の立場におごり高ぶることのないよう、どんな立場にあっても学ぶことを忘れるな。」ということなのだと思います。今でも、人とのかかわりを通じて、学びは自分の背中を押してくれていますね。
少し前に修行場のリニューアルをしました。