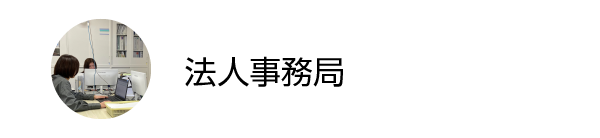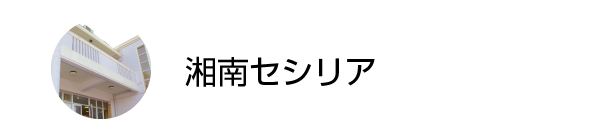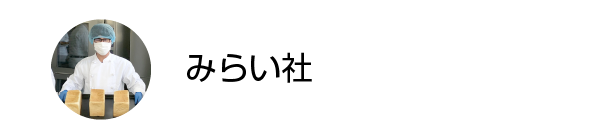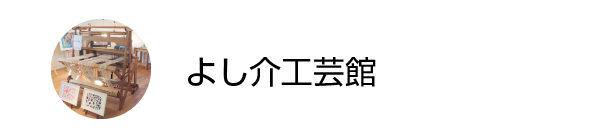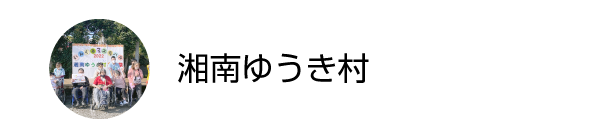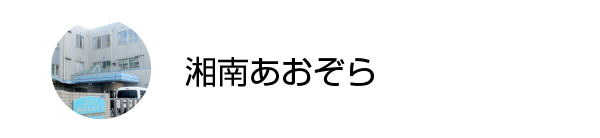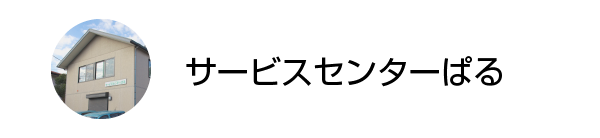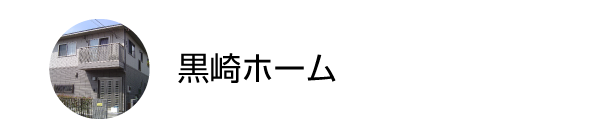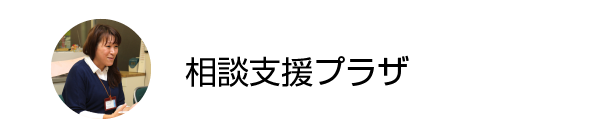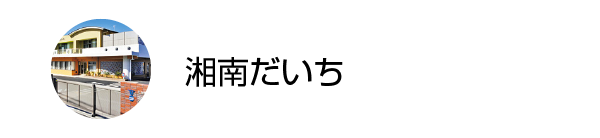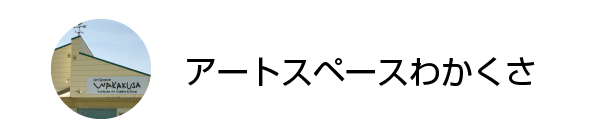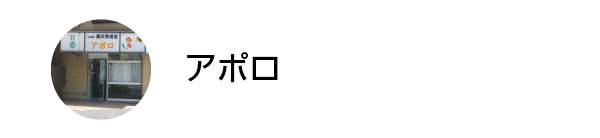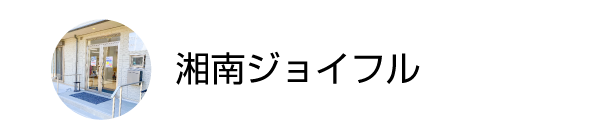日記
- HOME
- 施設長・課長日記
施設長・課長日記
骨髄提供体験記⑤(湘南ゆうき村・法人事務局 課長 高橋宏明)

前回までの体験記はこちら
【入院2日目(手術当日)】
5時30分、緊張からか普段より早く目覚め、術前最後の水分補給(OS-1)をする。
(6時過ぎに起きていたら飲めなかったので、体内時計に感謝)
6時、看護師が来てOS-1の摂取量を確認され回収。
8時半、手術着を着るよう指示があり、弾性ストッキングを履いて待つ。
目出し帽の足バージョンが気に入り、記念撮影。(捨てずに持ち帰った)
9時、看護師さんに呼ばれて手術棟へ。
手術棟の手前に待機室があり、
この時間帯に手術する人が、5人集まった。
順番に名前が呼ばれ、各々手術室へと向かう。
こんなに手術する人がいるんだなと思っていると
3番目に呼ばれ、いよいよ手術室のあるフロアへ。
正面に窓があり、明るくて広く、とても清潔感のある空間。
「手術室までの通路に大きな窓がある病院って珍しいんですよ」
なんて説明を受けながら手術室へ歩く。
手術室の前には、麻酔科の先生と看護師がスタンバイしていて、
名前・生年月日・手術名を最終確認され、手術室へ。
いよいよだ。
※写真は年末年始に帰省した妻の実家山形の雪景色
「標準的支援」(湘南ゆうき村・湘南だいち 施設長 妹尾貢)

「強度行動障害の標準的支援」という言葉があります。行動障害の予防や、現に起きている状態を改善するための支援の方法として、近年、研修等でよく説明されている考え方です。
藤沢育成会では、平成17年に「行動援護」というガイドヘルパーの制度が創設された時から、「行動援護従業者養成研修」を実施してきました。行動援護のサービスを提供するためには、ヘルパーさんがこの研修を受講する必要性があり、以前からガイドヘルパー研修など自前で研修を実施することが自然な流れだったこともあって、サービスセンターぱるが行動援護研修の事務局を担当してきました。
平成25年からは、国がこの研修を他のサービスの従事者のための「強度行動障害支援者養成研修」という研修に再編し、「基礎研修」と「実践研修」の2階建て方式になりました。この研修も、平成27年度から藤沢育成会で実施することになりました。
これらの2つは、元のカリキュラムは同じものなのですが、地域の支援の充実のために、行動援護ヘルパー向けにキャパシティを確保しておく必要があると判断し、育成会では別々に実施しています。
これら2つの研修共通で、基本的な考え方・方法として学んでいるのが、この「標準的支援」です。
「強度行動障害を有する者への支援にあたっても、知的障害や自閉スペクトラム症の特性など個人因子と、どのような環境のもとで強度行動障害が引き起こされているのかなどの環境因子もあわせて分析していくことが重要となる。こうした個々の障害特性をアセスメントし、強度行動障害を引き起こしている環境要因を調整していくことが強度行動障害を有する者への支援において標準的な支援である。」
※強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会報告書(令和5年3月30日) より)引用
上記研修では、この考え方を講義と演習を組み合わせて学んでいきます。この研修を全国で、すでに10万人以上の従事者が受講済みだということで、昨年度からは支援の現場での技術の定着を目的に、施設での支援の核となる人を育成するための「中核的人材養成研修」を国主体で開始し、育成会からも受講生とスタッフとして、それぞれ参加しています。中核的人材研修ではより実践的な内容を、実際の支援の現場とのやり取りで身に着けていくと同時に、外部コンサルテーション(広域的人材)と一緒に利用者を支援して状態を改善していくためのネットワークも作っています。すでに行動障害の状態になっている人を支援していくためには、多様な人材の力が不可欠だからです。
福祉現場の従事者の処遇改善の動きも活発ですが、働き甲斐・やりがいとは、処遇面だけではないと思っています。業界として、それら社会の期待に応えられる専門性を持つことが、この仕事の魅力を高めることになります。我々の仕事の専門性が理解されるということは、自閉症や発達障害、知的障害のある人の生きにくさや、配慮の仕方についての理解も進むということだと思っています。
今年の2月~3月には、神奈川県の委託をうけ、「行動障害を予防するための研修会」を予定しています。3回目(3月20日)の日程は若干の空きがありますので、ぜひご参加ください(詳しくは、法人ホームページ「法人からのお知らせ」をご覧ください)。
(写真は、年末に相模湖にワカサギを釣りに行った際の「ワカサギハウス」。雲一つない釣り日和でしたが...釣果は聞かないでください。ブラックバスが釣れました!)
「続いていく時間」(サービスセンターぱる 課長 飯原 佑)
年末、今年も近所の方と集まり、ゲームをして過ごしました。
以前の日記でも触れましたが、もともとは挨拶を交わす程度だったご近所の関係が、少しずつ形を変え、こうして年末に集まるようになりました。気づけば、この時間も2年連続になっています。
今回遊んだのは「桃太郎電鉄」という、サイコロを振って日本各地を巡りながら目的地を目指すテレビゲームです。
昨年は思うようにいかず、資金が減る一方で終わったことをよく覚えています。
その話は今年も自然と話題に上がり、笑いながらのスタートとなりました。
ゲームは単純そうに見えて、流れはなかなか読みきれません。
順調に進んでいると思ったところで状況が変わり、少し油断すると一気に形勢が逆転します。
それでも、同じ画面を囲み、同じ展開に一喜一憂する時間は心地よく、気づけば時間はあっという間に過ぎていました。
こうして無理のない関係が続いていることに、改めてありがたさを感じます。
特別なことをしなくても、同じ時間を共有するだけで、関係は少しずつ深まっていく。
以前書いた近所付き合いの話も、こうした積み重ねの延長にあるのだと思います。
日々の仕事においても、人との関わりは同じように築かれていくと感じています。
多くを語らなくても、同じ場で同じ時間を過ごす中で生まれる安心感が、その人らしさを尊重した関わりにつながっていくことがあります。
結果として、今年も大きな勝敗の変化があったわけではありませんが、
また来年へと続いていく時間になりました。
こうした何気ない積み重ねを大切にしながら、年末を締めくくりました。
今回の写真も、近所の方々と遊びに行ったマザー牧場で撮った写真です。
総勢20名以上で行き、楽しく過ごせました。
謹賀新年(黒崎ホーム 課長 髙橋克之)

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
皆さんは年賀状を送りましたか?我が家では徐々に数を減らし、今年はわずか数枚にまで減りました。自分自身の負担が減り良かったと思う反面、少し新年っぽさがなくなってしまったような寂しい気持ちもあります。
私がまだ子供の頃、家には大量の年賀状が届いていました。自分の分と親に来た分を比べると圧倒的に自分が少なく、いつかは追い抜いてやろうと思っていたものです。時が経ち、自分が大人になると年賀状の数は増えていきましたが、もらう数が増えると当然こちらから送る数も増えていきました。増えるといっても20枚程度でしたが、それでも毎年ひいひい言いながら書いたものです。
人は誰かの成しえた成果を見て、うらやましがったり妬んだりする事があるものです。しかし、その成果の裏には沢山の苦労や困難があり、それを乗り越えたからこそ目に見える成果が得られます。昔、両親は一体どれくらいの年賀状を書いていたのか。筆不精の私としては考えるだけでもぐったりしそうです。
新年に届いた数枚の年賀状。それを見て寂しさを覚えつつも、やはり良い時代になった、としみじみ感じた朝でした。
写真は1月1日0時に行った近所の神社です。初めて行ってみましたが、こんなに人がいるのかと驚きました。
「笑声」(サービスセンターぱる・黒崎ホーム 施設長 三嶌悟)

2025年も残すところあとわずかとなりました。今年も様々な出来事があったかと思います。私の中では、黒崎ホーム及びサービスセンターぱるの所長としての異動が大きかったです。
さて少し前の話ですが、黒崎ホームの世話人採用面接での一幕でした。面接に来た方が、笑顔で明るく親しみやすいトーンで話をされていて良い印象を持ちました。面接の中で「笑声」を意識しているとのことでした。
「笑声」の呼び方は「えごえ」といいます。「えごえ」を検索してみると、「声のトーンや息遣いから話し手の笑顔が伝わるような明るく親しみやすい声」のことと書かれていました。主にコールセンター業務や接客、面接時に使われることが多いようです。
「笑声(えごえ)」の効果としては、相手に好印象を与え、安心感や親近感を抱かせる効果もあるようです。
2025年も皆さんに支えられたことに感謝すると共に、2026年もよろしくお願いします。「笑声」も意識しながら精進していきます。
*写真は、サービスセンターぱる事務所前の階段です。冬の情景を彩ります。
「加湿器と除湿器」(湘南あおぞら・アポロ 課長 高橋羽苗)
寒い季節になると毎日湿度を気にしています。
喉が弱めなことに加えて静電気が嫌。思いもかけないところでバチっとくると一瞬で気持ちがすさみます。
とにかく湿気を目で見て感じたくて、加湿器はスチーム式一択。電気代は高くつく...と聞いても、あのもうもうとした白い蒸気に心強さを感じます。
夜から、がんがんにスチームをまきちらし、朝の窓がびっしゃびしゃに結露しているのを確認して「今日もしっかり加湿された」と一人で安心。
そのあと、雑巾片手にふき取っている時にはなんとなくバカらしくもないこともないけれど、ここまでやると小さな達成感。
一方で、季節が変われば除湿器が支え。じめっとした空気で気持ちも晴れないし、体調もいまいち。洗濯物もいつまでもすっきり乾かない...。
そんなときに旧式の除湿器が「ぼぉーっ」とすごい音を立てて動くのを応援して頼りにしています。その除湿器に溜まった水を捨てるときは、なんともいえないやりきった感と満足感。
一年を通して、こんなに湿度が気になる原因の一つと思っているのが、友人からもらった時計についている湿度計。見なきゃいいのに気になって、結局こまめにチェックしてはそわそわしています。
写真は、いつかの山の中。天気はいまいちですが、しっとりちょうどいい空気でした。